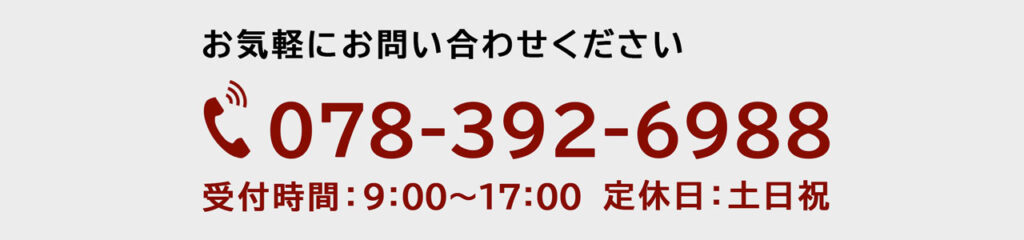1964年、東京で開催されたオリンピック。
その開会式で、世界中の注目を集めたのが「聖火台への点火シーン」でした。
この聖火台製作には、鋳物の伝統技術を受け継いだ職人たちの情熱とドラマが秘められていました。
本記事では神栄株式会社のルーツ、「高品質な鋳物製品づくり」にも深く関わる、聖火台製作の裏側を紹介します。
鋳物業界の巨匠・鈴木萬之助氏とは
鈴木萬之助(すずき まんのすけ/1882~1966年)氏は、日本の鋳造技術の発展に大きく寄与した名工です。
鋳造業界での長年の実績から、多くの技術者たちに尊敬されてきました。
大会組織委員会からの無理難題と製作の決意
1964年の東京オリンピック開催の決定後、日本は東京オリンピックの招致アピールを目的とし、1958年に開催するアジア競技大会のための聖火台製作を決定します。
大会組織委員会から提示された製作に関する条件は「納期3か月、製作費は20万円」。
当時、聖火台を作るためには最低でも納期は8か月、費用も提示条件の約20倍が想定された為、大手企業は軒並み、大会組織委員会からの製作依頼を断りました。
そこで大会組織委員会は当時の埼玉県川口市長を経由し、鋳物づくりの名工、鈴木萬之助氏を聖火台の製作者に指名しました。
萬之助氏は当時70歳を超えており、第一線を退いていましたが、『名誉な仕事』だと、この依頼を受けました。
製作中に起こった悲劇|湯入れ事故と萬之助氏の急逝
聖火台の製作に入った萬之助氏は、川口内燃機の社長であった岡村実平氏(後の川口市長岡村幸四郎の祖父)から作業場を借り受け、三男である鈴木文吾(ぶんご)氏を誘い、依頼から2か月後に鋳型を完成させました。
しかし、湯入れ 作業中、圧力に負けてボルトが吹き飛び、鋳型に穴が空いたことで爆発事故が起きてしまいます。
このショックと過労で8日後に萬之助氏は急逝してしまいます。
聖火台完成まで残された時間は、わずか1か月でした。
息子たちによる奇跡の完成|聖火台製作の成功
文吾氏は兄弟と萬之助氏の教えを受けた周囲の職人たちの協力に支えられ、不眠不休で2度目の注湯を行い、成功。
その2週間後に聖火台を作り上げ、見事、聖火台は国立競技場の南側スタンド上部へ設置されました。
そして、アジア競技大会6年後の東京オリンピックでも聖火が灯されたのです。

聖火台に描かれている20の横線は、アジア競技大会での参加国・地域の数、波模様は太平洋を表しています。
萬之助氏が急逝した際、事実を知り、動揺して仕事ができなくなったらいけないと周囲は文吾氏に萬之助氏の死を伝えなかったといいます。
これは家族にとって苦渋の決断でした。葬儀当日に父の死を知った文吾氏はあわてて葬儀に向かいましたが、父の顔を見ることはできませんでした。
聖火台製作が成功した当時、文吾氏は、「もし自分まで失敗したら腹を切って死ぬつもりだった」とコメントしています。
聖火台のその後|保存と現在の設置場所
鈴木萬之助氏と文吾氏が作成した聖火台は1964 年東京オリンピック大会時に国立競技場バックスタンド(東側)最上段に移設され、大会期間中聖火が灯されました。
のちに聖火台は、文吾氏の手により製作者名として父・萬之助氏の名を指す「鈴萬」の文字が彫り込まれ、国立競技場が解体されるまで設置されました。また、2013年9月8日には2020年五輪招致成功を祝って火がともされました。

国立競技場の解体から新国立競技場の建設の間は東日本大震災の被災地等に貸し出され、2015年から宮城県石巻市、その後は岩手県、福島県へと貸し出しが行われました。
そして、2019年に製造地である埼玉県川口市に戻り、2020年3月まで川口駅東口公共広場で展示されました。
展示終了後、現在は、国立競技場のシンボルとして、新国立競技場の東側ゲート正面へ移設されています。
文吾氏は2008年に86歳で他界しましたが、弟の昭重氏が遺志を継ぎ、聖火台の保存に尽力。昭重氏は2020年東京オリンピックの聖火ランナーにも選ばれました。
聖火台をめぐる命懸けのドラマは現在も後世へと語り継がれています。
1964年東京オリンピックの聖火台製作には、鋳物技術の伝統と職人魂が息づいていました。
神栄株式会社では、これからも高品質な鋳鉄フレーム・ギア部品の製造を通じ、日本のものづくりを支え続けていきます。

神栄株式会社は、ベトナム・タイのローカル協力工場から鋳物及び金属製品を輸入販売しております。
ベトナムから8年以上、タイからは約40年以上の輸入実績があり、豊富な経験を持つスタッフを多数有しています。
リスクヘッジとコストダウンとして、ベトナム・タイからの調達をご検討頂きますようお願いいたします。

今後も現地スタッフと連携し、引き続き貿易、生産、コスト低減、リスクヘッジなど、鋳物CHINA+ONEでお客様により良いサービスを提供できるように、努力をしていきたいと思いますので、是非、タイ、ベトナムにお越しの際は、現場の視察に足を運んで頂ければ幸いです!